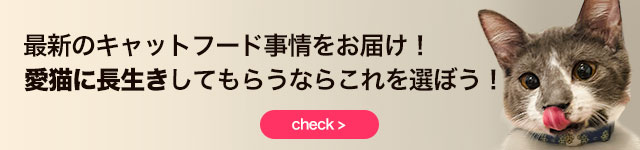外飼いの猫ちゃんは特に喧嘩によるケガが多いですが、室内飼の猫ちゃんであってもケガをしてしまうこともあります。
万が一、愛猫がケガをしてしまった時の応急処置や、ケガをしないための予防方法を知っておく必要があります。
ここでは猫に多いケガや予防策について解説しています。
執筆・監修

獣医師
麻布大学獣医学部獣医学科卒業後、動物看護士・トリマーの専門学校で教員を行う傍らトリミングのライセンスも取得。その後、ペット保険会社、動物病院向けの専門商社に勤務。現在は2児の母で子育て奮闘中です。
nademoの公式LINEアカウントでは、お友だちを募集中!
大切なうちの子との生活に役立つ情報や、nademoの最新情報をお届け♪
プレゼント企画やお友だち限定企画も用意してありますので、友だち追加お待ちしております!
目次
猫がケガをする主な原因

猫に多いケガは「外傷」「脱臼・捻挫・骨折」です。
外傷の原因
なんといっても他猫との喧嘩によるケガが圧倒的に多いです。
喧嘩は以下の2つが主な要因となり発生しますので、その状況を作らないようにすることも大切です。
| テリトリーの侵害 | 自分の縄張りに他猫が侵入してきた場合、排除するために喧嘩をしてしまいます |
| メス猫の取り合い | 発情期のオス猫がメス猫を取り合い喧嘩をしてしまいます |
脱臼・捻挫・骨折
外であれば、交通事故・高所からの転落事故などでおこることが多く、室内であれば人に踏まれてしまったり、太りすぎや栄養失調による骨折・着地の失敗での捻挫・脱臼などが主な要因としてあげられます。
猫の主なケガの種類・症状

前述のケガ以外にも猫に起こりうるケガの種類と症状についてご紹介します。
噛み傷
猫の歯は長くて鋭いため噛まれた傷口は小さく、一見するとあまり深いケガに見えなかったり、すでに傷口が塞がっていることもあります。ですが、実際は深く筋肉まで達していることも少なくありません。
猫の歯は細菌が多く付着しているため、放っておくと細菌感染を起こし、化膿・炎症を引き起こします。
ひっかき傷
噛み傷ほど深い傷になることは少ないですが、傷口からの細菌感染による化膿・炎症は注意が必要です。
捻挫・脱臼
室内外問わず、事故・転落・転倒・衝突・急な方向転換など、関節に負荷がかかることによって生じます。
足を引きずっていたり、腫れや熱感、歩くのを嫌がるなどの症状がみられた場合は脱臼や捻挫を疑いましょう。
また、脱臼は股関節と尻尾の付根部分で発生することが多く、尻尾の付根部分で起こった場合は排泄がうまくいかなくなることもあります。
骨折
交通事故や高所からの転落事故など強い衝撃を受けた時に骨折をすることがあります。
また、低栄養や肥満などの栄養状態の悪化や骨の腫瘍などでも骨折をすることもあります。
骨折は強い痛みを伴いますので、脱臼や捻挫よりも気が付きやすいですが、早急に動物病院への処置が必要となります。
激痛のほかにマヒや骨の変形を伴うことが多く、骨折場所によっては呼吸困難になったりと症状は様々です。
やけど
ホットカーペットなどの暖房機器によるものや、お風呂への落下事故などが原因でやけどをすることがあります。
飼い主さんができる愛猫のケガの応急処置

応急処置をしようとすると傷が痛くて暴れたり噛みついたりして抵抗するケースが多い為、タオルで包んでから処置を行うなど、飼い主自身が嚙まれない状況を作ることが大切です。
一般的に動物は人間よりも痛みに敏感と言われています。
また、動物病院に連れていくまでの間、患部を舐めさせないようにしましょう。
噛み傷・ひっかき傷
まずは患部を見つけ、出血量を確認します。
出血が少ない場合
汚れている場合は流水で汚れを洗い流し、ガーゼやタオルなど清潔な布を当てて止血しましょう。
特に嚙み傷の場合は出血が少なくても、内部で感染がおこっている可能性がありますので、動物病院を受診しましょう。
出血が多い場合
通常サイズの猫の場合は、250cc前後位の血液量しかなく、人間の出血と比べると少しの量であっても猫にとっては大出血になります。
猫の意識がなかったり、ぐったりしているのであれば、できる限り早く動物病院を受診しましょう。
捻挫
腫れや発赤が確認できる場合、できる限り患部を動かさずに氷水などで冷却します。
脱臼や骨折との区別が難しい場合は動物病院を受診することをお勧めします。
脱臼・骨折
骨折や脱臼の場合は添え木をあて、周辺の関節部分ごと動かないように包帯などで巻いて固定します。強く巻きすぎると血流を阻害してしまうため、注意が必要です。
添木などが難しい場合にはケージなどに入れ、幹部を動かさないように急いで動物病院に連れて行きましょう。
やけど
まずは患部を冷水や氷、冷たい濡れタオルなどで熱感がなくなるまで冷やします。猫は体毛で覆われていますので、痛がらない程度に毛をかき分けて患部を冷やします。
重度のやけどで皮膚がめくれてしまっていたり、水ぶくれが出来てしまっているときは患部を冷やしながら直ぐに動物病院に連れて行きましょう。
愛猫のケガに気付いたときの注意点

猫はケガや病気を隠すのがとても上手で回復力も強い動物です。
そのため、飼い主が注意深く観察し、いつもと様子が違っていたり、元気や食欲がなかったり、と少しの変化に気が付いてあげることがとても重要です。
病院嫌いな愛猫も多いかと思いますが、飼い主の判断で投薬や処置を行うことはとても危険ですので、必ず動物病院でみてもらいましょう。
あわせて読みたい
愛猫のケガの予防策

ケガの種類に応じて、事前にできるケガの予防策をそれぞれご紹介します。
外傷の予防方法
外飼いの猫の場合は去勢手術をすることで発情期がなくなり、メスの取り合いによる喧嘩は減らせると思います。
室内での多頭飼いなどの場合はそれぞれの猫の性格を把握し、テリトリーを守ってあげることが大切です。
あわせて読みたい
あわせて読みたい
捻挫・脱臼・骨折の予防方法
フローリングなどの滑ってしまう床は、ラグやマットを敷くことでケガの予防に繋がります。
高いところから飛び降りることを防ぐためにキャットタワーを設置するなどして、高いところから下りれるステップを設けましょう。
また、骨折や落下事故は栄養失調や肥満が原因になることもあるため、日頃から栄養状態を管理することを心掛けてください。
やけどの予防方法
ストーブなどやけどの恐れがある暖房器具には近づけないように、柵などを設置しましょう。
この記事の執筆者・監修者
執筆・監修者の情報
※ 記事内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がnademoに還元されることがあります。
※ 監修者は掲載情報についての監修のみを行っており、掲載している商品の選定はnademo編集部で行っております。
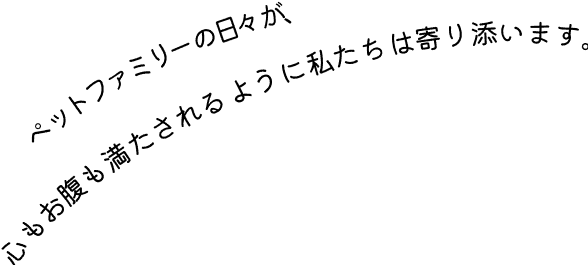
![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://stage02.nademo.jp/wp-content/uploads/ヘッダーロゴ.png)
![ペットメディア【nademo [なでも] 】犬・猫・小動物との生活を応援](https://stage02.nademo.jp/wp-content/uploads/ロゴ_2.png)